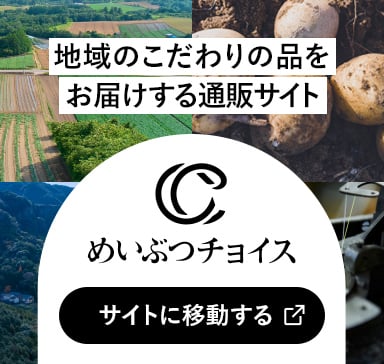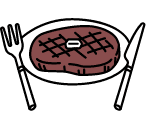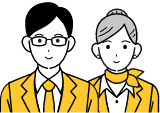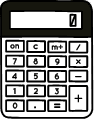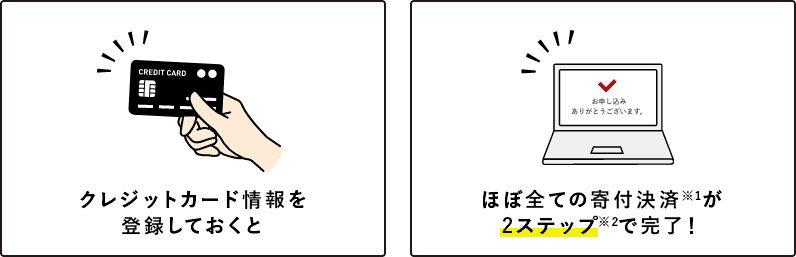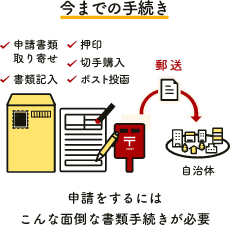チョイス限定 草木染め キット KUSAKIZOME KIT

お礼の品について
| 容量 | ・OTEFUKI(SARASHI) (37cm×104cm)…2枚 ・インド茜 ・槐(エンジュ)の花蕾 ・輪ゴム…5個 ・ビー玉・・・3個 ・ビニール手袋…Mサイズ1セット、Sサイズ1セット ・みょうばん・・・2袋 ・KUSAKIZOME KITのこしらえ方説明書 |
|---|---|
| 事業者 | 株式会社 京屋染物店 他のお礼の品を見る |
| お礼の品ID | 5497426 |
お申し込みについて
| 申込条件 | 何度も申し込み可 |
|---|---|
| 申込期日 | 通年 |
| 発送期日 | 決済から1ヶ月程度で発送 |
| 配送 |
|
京屋染物店は岩手県南の城下町「一関(いちのせき)」で100年続く染物屋です。
世界遺産平泉の浄土思想や伝統芸能、数多くの伝統工芸品が生まれたこの地で、お客様だけの手拭いを想いやこだわりに寄り添い、心を込めて大切に作り上げています。
家庭で気軽にできる草木染めのキット。
茜の根と槐(エンジュ)の花蕾、二種類の草木染めを楽しめるセットです。
en・nichiのOTEFUKI(SARASHI)を2枚お付けしています。お手持ちの綿100%生地でも染色可能です。
OTEFUKI - sarashi -
「オーガニックコットン100%」の、無地の手ぬぐいです。
一般的な生地は、より白く美しく見せるために"蛍光染料"が使われますが、この蛍光塗料は有害物質を
含んでおり、肌に悪いとされています。この晒(さらし)生地は"蛍光染料を使わず、オーガニックコットン
100%"で特別に作っていただいており、赤ちゃんでも安心して使える手ぬぐいとなっております。
草木の色は一期一会。
日本には豊かな自然が存在し、四季折々に様相を変え私たちの生活に彩りを与えてくれます。
草木の種類、産地、収穫シーズン、そして一つ一つそれぞれの生命力によって色みに違いがあります。
個性豊かな自然の恵みをたっぷりと感じながら、お家で簡単にできちゃう草木染め、正直言って贅沢。
”赤い根”だから茜。
日本では古くから赤系の染料として親しみがある茜。”赤い根”から名付けられた名前の通り、草木染めでは
根っこを使います。
”幸福”の槐(エンジュ)。
夏に白い花が咲く槐。草木染めでは槐の花蕾を使います。花言葉の中に”幸福”という意味があり、願掛け
として生地をお守りとして使うのも素敵ですね。
【事業者】株式会社 京屋染物店
KUSAKIZOME KIT
家庭で気軽にできる草木染めのキット。
茜の根と槐(エンジュ)の花蕾、二種類の草木染めを楽しめるセットです。
京屋のOTEFUKI(SARASHI)を2枚お付けしています。お手持ちの綿100%生地でも染色可能です。
セット内容
・OTEFUKI(SARASHI) (37cm×104cm)…2枚
・インド茜
・槐(エンジュ)の花蕾
・輪ゴム…5個
・ビー玉・・・3個
・ビニール手袋…Mサイズ1セット、Sサイズ1セット
・みょうばん・・・2袋
・KUSAKIZOME KITのこしらえ方説明書


草木の色は一期一会。
日本には豊かな自然が存在し、四季折々に様相を変え私たちの生活に彩りを与えてくれます。
草木の種類、産地、収穫シーズン、そして一つ一つそれぞれの生命力によって色みに違いがあります。
個性豊かな自然の恵みをたっぷりと感じながら、お家で簡単にできちゃう草木染め、正直言って贅沢。


”赤い根”だから茜。

日本では古くから赤系の染料として親しみがある茜。”赤い根”から名付けられた名前の通り、
草木染めでは根っこを使います。
”幸福”の槐(エンジュ)。

夏に白い花が咲く槐。草木染めでは槐の花蕾を使います。花言葉の中に”幸福”という意味があり、
願掛けとして生地をお守りとして使うのも素敵ですね。
KUSAKIZOME KITの使い方(YouTube)
| カテゴリ |
ファッション
>
小物
>
ハンカチ・スカーフ
雑貨・日用品 > その他雑貨・日用品 > |
|---|
- 自治体での管理番号
- ichinoseki01132
- 地場産品類型
3号
一関市について
◆市の紹介
本市は、岩手県の南端に位置し、南は宮城県、西は秋田県と接しています。
首都圏からは450キロメートルの距離で、東北地方のほぼ中央、盛岡市と仙台市の中間地点に位置しています。
一関市の総面積は1,256.42k㎡であり、東西は約63km、南北は約46kmの広がりがあります。
人口は118,015人(H30.8.1現在)で、人口、面積とも岩手県で2番目の規模となっています。
◆歴史・沿革
本市の歴史は古く、平安時代には安倍氏、藤原氏が独自の文化を築き上げ、その後葛西氏、伊達氏、田村氏の治世下に置かれました。
明治の近代化以降の地域の成り立ちは、廃藩置県によって、胆沢県、一関県、水沢県、磐井県と変遷し、明治9年に岩手県に編入されました。
昭和の大合併によって合併前の8市町村となり、平成17年9月に1市4町2村が新設合併、平成23年9月に編入合併し現在に至っています。
◆自然
本市は、四季折々に多彩な表情を示すめぐみ豊かな自然に包まれています。
市の西側にある栗駒山の周囲には深い森が広がり、湯量豊富な須川温泉をはじめ多くの温泉に恵まれています。
市の東側にある室根山をはじめ緩やかな丘陵地が広がる北上高地は穏やかな隆起準平原で、なだらかな高原には牧場が各所に開かれています。
北上平野の南端部にあたる市の中央部には標高の低い平地が広がり、東北一の大河北上川が緩やかに流れています。
北上川の支流、磐井川の中流域には渓谷美を誇る厳美渓、砂鉄川には石灰岩地帯を深く刻み込んだ猊鼻渓があり多くの観光客が訪れる名所となっています。
◆文化
本市には、世界文化遺産「平泉」の関連遺産として世界遺産暫定リストに登載されている骨寺村荘園遺跡があるほか、平泉文化にゆかりのある遺跡などが各地に残されています。
また、古くから受け継がれてきた南部神楽をはじめとする伝統芸能や行事が数多く息づいているとともに、国指定重要無形民俗文化財の室根神社祭のマツリバ行事、県内有数の規模を誇る川崎地域の花火大会、奇祭として知られる大東大原水かけ祭りや縄文の野焼きを再現した藤沢野焼祭など各地で行われる独特の祭りも豊富です。
古くから冠婚葬祭や農作業の節目、季節の行事などの場面で、もちをついてふるまう「もち食文化」があります。

岩手県 一関市