人から人へ、だんじり担う。伝統と若者が交わり、漁師町の未来を担うだんじり祭りを復活させたい!
カテゴリー:観光・PR
寄付金額 1,143,900円
目標金額:2,000,000円
- 達成率
- 57.1%
- 支援人数
- 61人
- 終了まで
- 受付終了
島根県海士町(しまねけん あまちょう)
寄付募集期間:2024年9月6日~2024年11月2日(58日間)
海士町 崎(さき)区

崎地区は、島根県の離島海士町の南端に位置する約80世帯、156人が暮らしている集落です。
11月に海士町崎地区にて、「崎村だんじり」が行われます。通称は「崎村だんじり」ですが、正式には「恵比須祭の風流(ふりゅう) だんじり」。海士町の指定無形民俗文化財です。
崎村だんじりは、豊漁祈願をする為に、崎地区の住民たちが老若男女ともに一緒になって集まる場所。8年前に実施された際も、ひとつの大きなだんじりをみんなの力で担いで練り歩いたことで、崎地区民の一体感がより一層深まった実感があります。崎地区民がみな漁師町としての誇りを思い起こし、そして豊かな暮らしを盛大に感謝するきっかけを作る為にも、崎だんじり祭りの復活が必要です。

荒波を乗り越える!崎地区の伝統行事「崎村だんじり」
「崎村だんじり」の由来は、北前船が盛んに隠岐海峡を航海した当時の乗組員が西ノ宮の「えびす祭りだんじり」を見て感動し、「崎村十日えびす祭り」でもこれをやりたいということになり始めたものと言われており、約200年以上の歴史を持つ崎地区の伝統行事となっていました。
崎村だんじりは、大漁を祈願して実施してきたお祭りです。
地元の小学生4名を屋台(だんじり)に縛り付け、約45人の青壮年が担いで左右に傾けながら練り歩く形式で行なわれます。
子供が乗っているだんじりの揺れはかなり激しいことから、漁師の多い崎地区では昔から、これを経験することが荒波に負けない一人前の漁師になる登竜門だと考えられていました。だんじりというと山車を想像しますが、崎地区は道が狭く坂も多いので、屋台を担ぐ珍しいスタイルとなっています。

崎村だんじりは、子供達と担ぎ手だけではなく、お囃子の「音頭取り」、屋台を飾り付ける「飾り花」、ハライッチャ踊りの「踊り手」、直会(なおらい)の準備・片付けなど、区民それぞれに役割があります。
この祭りは200年間、崎地区の大漁を願い、そして、崎地区の団結を強める機会としても大切に守り継がれてきました。
※ハライッチャ踊り…だんじりに飾り付けられた椎の小枝を手に取って、ハラエッチャと歌いながら祭りが終わります。神様の使い(神の子)を無事に納めて、皆で務めを果たした後にほっとしたお祝いの雰囲気で踊るようにと言われているそうです。

幾度となく、祭りが中止となった過去
しかし、1980年代まで、過疎高齢化により若者が流出し、担ぎ手不足等で催行が困難となり、長らく祭りの開催が途絶えていた時期がありました。
この期間を経て、地域文化継承の必要性を痛感した区民は、話し合いを重ね、平成24年から4年に一度の大祭りとしてオリンピック開催の年にあわせて崎村だんじりを執り行うことを取り決めました。
しかし、その後の新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により、令和3年は開催中止を余儀なくされました。最後に祭りが開催されたのは、平成28年のことでした。
残念ながら、この8年間の中止期間のあいだに崎村だんじりのことを知っている人が随分と減ってしまいました。今年、崎村だんじりが実施されなければ、継承されることなくお祭り自体が消滅してしまう危機にあります。
崎村だんじりは、豊漁祈願をする為に、崎地区の住民たちが老若男女ともに一緒になって集まる場所。8年前に実施された際も、ひとつの大きなだんじりをみんなの力で担いで練り歩いたことで、崎地区民の一体感がより一層深まった実感があります。崎地区民がみな漁師町としての誇りを思い起こし、そして豊かな暮らしを盛大に感謝するきっかけを作る為にも、崎村だんじり祭りの復活が必要です。
そこで、パリオリンピックが催行された令和6年。4年に1度の大祭りに向けて、区内外と共に協議と準備を重ね、11月3日の文化の日に祭りが開催できることとなりました!
祭りの未来を担うのは、漁業を中心に崎地区に集う若者たち
この8年間で崎地区内に大きな変化がありました。それは、崎地区に若者が増えたということです。
崎区には海士町内で最大の定置網基地があり、現在は10名程度のUIターン者が日々出漁、海士町の水産現場を支えています。
先人たちから受け継いだ漁法を継承しながらも、沖垣網という網の設置によって漁獲量を増加させるなど、若い漁師たちが新たな取組に挑戦し続け活気ある漁港となっています。

また、海士町最大の定置網基地があり豊富な漁獲が安定してあることから、町の施策のひとつとして、崎地区に島の食材のみで日本料理を学ぶ料理学校「島食の寺子屋」が設立され、全国から日本料理を学ぶ若者が集まるようになっています。

近年では、3ヵ月~1年間ほど島暮らしを体験する「大人の島留学」制度を活用して、崎地区内で改修された空き家に住む若者も増えてきています。
地元民とUIターン者が集まる青年団の活動も活発で、海士町綱引き大会では7年連続で他地区を圧倒して優勝しているほかに、隠岐牛花火大会など島内から200人以上の参加者を集めるイベントを実施するなど、毎年のように崎地区の賑わいを創り出しています。
今回のだんじり祭りでは、青年団のメンバーで行なう前夜祭で打上花火大会も企画中です!

あらゆる垣根を越えて。一致団結して漁師町「崎地区」を盛り上げます!

お祭りには、音頭取り6名、担い手60名、神の子4名、飾り花10名、ハライッチャ踊り手20名等総勢約100名を超える人たちの一致団結が必要となります。
100名を越えるメンバーには、崎地区の地元の人だけでなく、定置網の漁師たち、島の青年団や婦人会、島の料理学校「島食の寺子屋」に通う学生、島暮らしを体験している「大人の島留学生」など、出身、年齢、性別、職場、崎地区に住んでいる年数も異なる人たちが垣根を越えて集結します。
垣根を越えてお祭りを実施したいのは、大漁を願う祭りを催行し続けることで、崎地区が漁師町として潤い続け、崎地区そして島全体の豊かな暮らしが続いていくことを願っているからです。
そして、初めてだんじりを担うことになる、移住者や若手にとって、島の大漁祈願を願うお祭りに深く触れることで、崎地区が第二の故郷となり、彼ら彼女らが島を出ることがあっても、いつかまた島に戻りたいなと、思ってもらえるきっかけになればと思います。
形だけの継承にならず、漁師町「崎地区」の未来を担いでいくお祭りにしていきます!
応援、ご支援の程宜しくお願いいたします!
寄附金の使い道
崎村だんじり運営費の一部に活用します。
【内訳】
・記録用ビデオ制作費
・担い手や神の子の衣類、履物代
・だんじりの飾り付け経費
・練習用経費
・ポスター・チラシ経費
・神事経費
・交通費
プロジェクト実施スケジュール
2024年 11月3日(日)崎村だんじり開催
*目標金額に達しなかった場合でも、本プロジェクトへ活用させていただきます。
*目標金額以上の寄附を頂いた場合、本プロジェクトの運営費として活用させていただきます。
崎地区の定置網漁労長 大窪さんからメッセージ

約8年ぶりの崎村だんじり開催が決まり、とても嬉しく思っています。
前回のだんじり祭りでは、大敷の大漁旗が掲げられていて、「地元の方々や神様に恥ずかしくないよう、しっかり漁をせねば!」と、奮闘させられたのを覚えています。今年は漁があったため、安心してお祭りを楽しめそうです。
大型定置網漁を行う上で、日頃より崎地区の皆さまには、様々な面でお世話になっています。
お祭りを通して、感謝を伝えられればと思います。
崎村だんじりが無事開催され、さらに漁が増え、崎地区がより活性していくことを、心より願っています。
海士町長 大江和彦 メッセージ

日頃より海士町を応援してくださり誠にありがとうございます。
海士町では島民一丸となって承前啓後の考え方を根底に「海士町の新時代」という次なるステージへ飛躍するため、島の様々な挑戦を推進しながら、一層魅力的な町を目指してまいります。
ガバメントクラウドファンディングを活用して、海士町創生総合戦略「エンジン全開計画(人口ビジョン)」に基づき、町の掲げる3つの「かん」(ひとの還流、暮らしの環境、里山里海の循環)を推進する新たな挑戦が増えていくことを願っております。
海士町の崎地区という一つの集落で、伝統を守りたいと立ち上がったこのプロジェクトをぜひあたたかい目で見守ってくださいますと幸いです。
海士町のまちづくりを応援してくださる皆様からのご協力を心からお待ちしています。
ふるさと納税で
このプロジェクトを応援しよう!
ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。
控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
控除上限額かんたんシミュレーション
お礼の品一覧
-

【のし付き】海鮮フライ 海士のいわがき・スルメイカ・豆アジの揚げ物3種 …
20,000 円
【海士町の海産物をフライで堪能できる盛り合わせセット】
島で取れる新鮮な海産物をフライにいたしました。
揚げるだけの簡単調理で、食卓に、お弁当に、さまざまな場面でお使いいただけます♪
・寒シマメ玄米粉唐揚げ
寒シマメのげそを海士町産の玄米粉を衣に使用して唐揚げにしました。
プリプリのげその食感と香ばしい玄米の香りを感じます。
・いわがきフライ
大粒のいわがきを贅沢に使用したいわがきフライです。
サクッとした食感の後にいわがきの旨味が口いっぱいに広がります。
・小さなアジフライ
地元飯古定置網で水揚げされる旬のアジは脂ののりも最高です。旬のアジを厳選してフライにしました。
小さいながらもしっかりと脂がのっていてアジの旨味が口いっぱいに広がります。
海鮮フライセット
【容量】
いわがきフライ4〜5個入り(計180g)、小さなアジフライ5〜6枚入り(計180g×2パック)、寒シマメ玄米粉唐揚(100g×2個)
【注目ワード】
海鮮 フライ アジフライ 牡蠣フライ カキフライ イカフライ いか イカ 牡蠣 岩牡蠣 島根県海士町
島根県海士町
現在進捗情報はありません。
島根県海士町
海士町は、日本海の隠岐諸島に位置する人口約2,300人の島です。
ユネスコ世界ジオパークに認定され、豊かな海、豊富な湧水など自然環境に恵まれ、自給自足のできる半農半漁の町で、鎌倉時代に後鳥羽上皇が島流しにされた場所でもあります。
「ないものはない」をスローガンに掲げ、近年は人口減少を食い止めるための多様な教育・交流施策の挑戦により、離島・過疎地でありながらも若者の賑わいが創出されています。


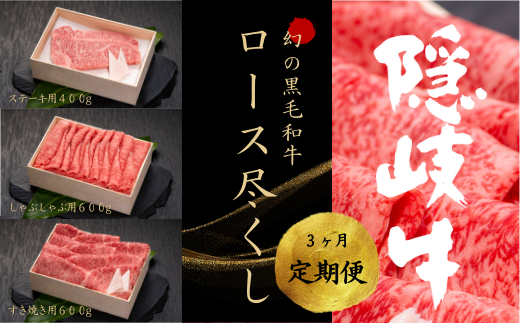



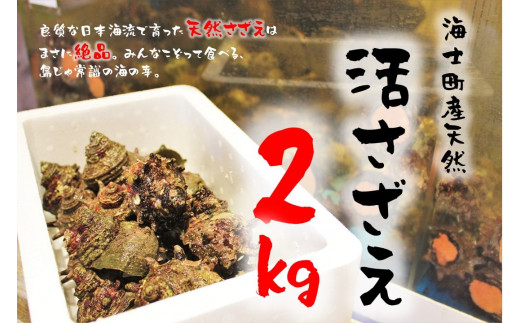


















































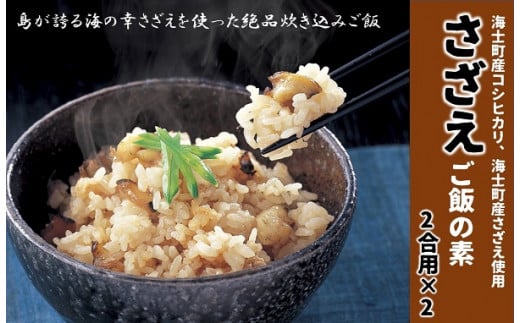







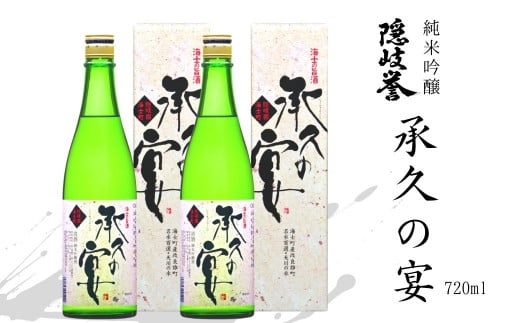




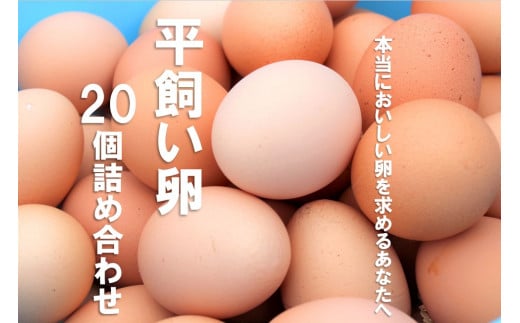

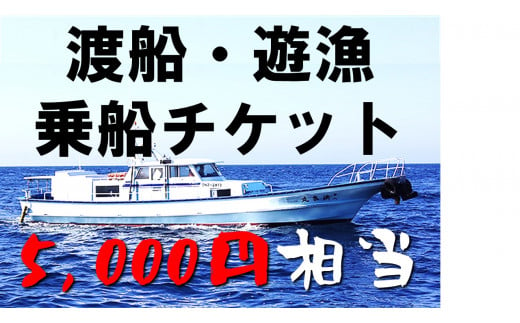
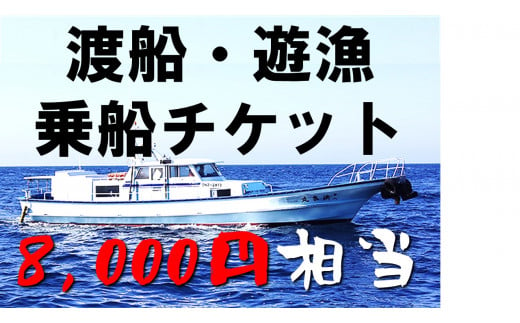
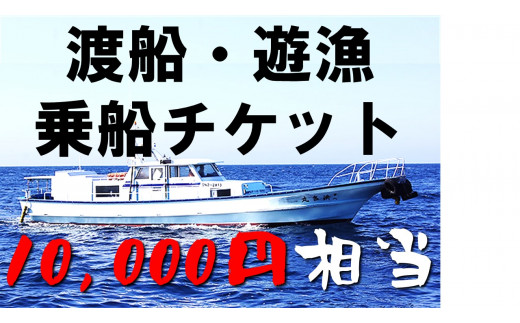
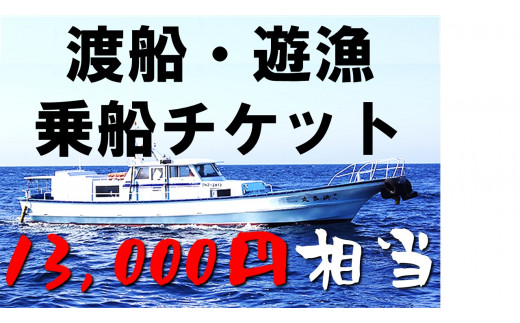
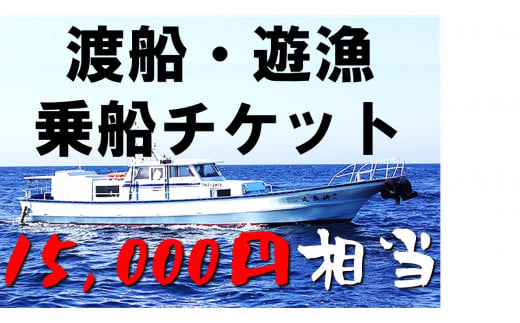

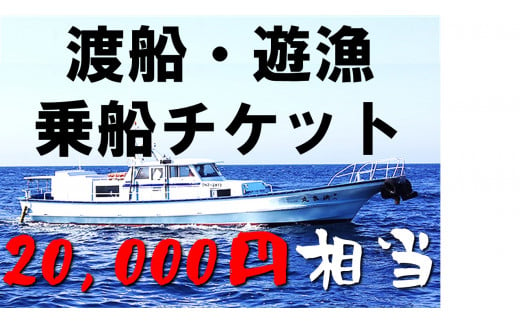
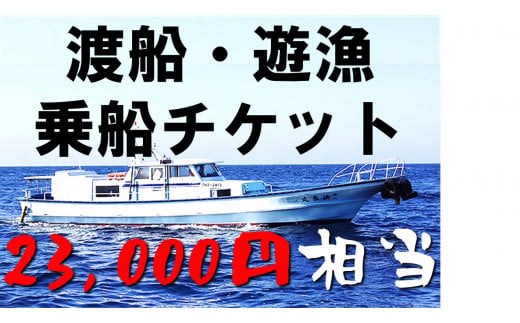
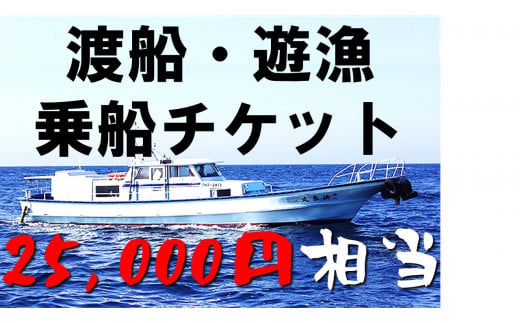

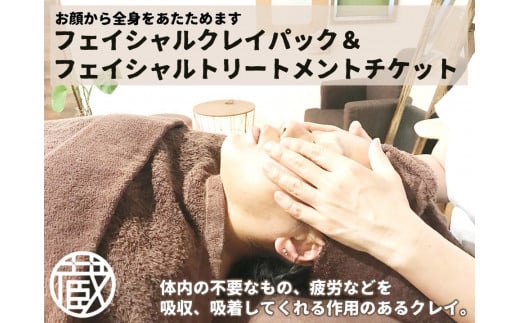









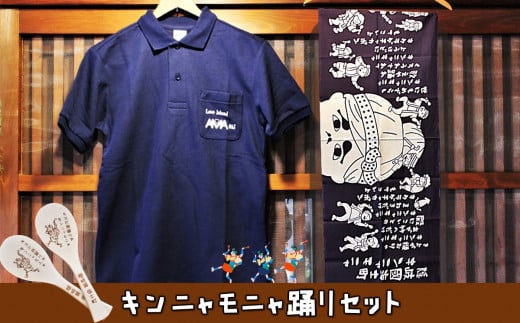
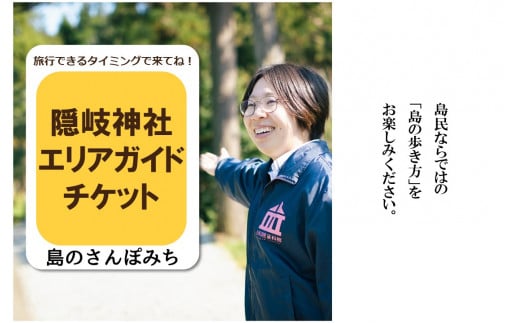




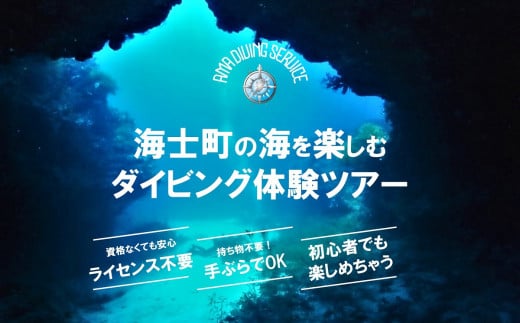



















































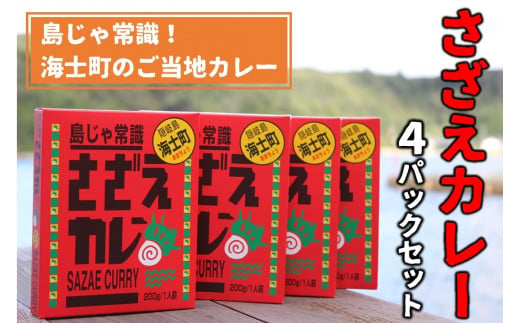















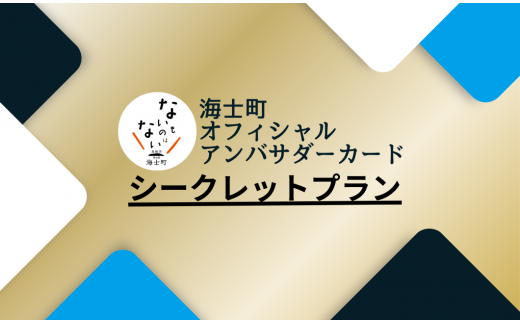







コメント投稿をありがとうございます!
あなたのその想いが
プロジェクトを動かしています。
投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。
反映まで数日かかることがあります。